
物流施設とは?種類・特徴から最新トレンド、活用戦略までを徹底解説

「物流施設の選定に迷っている」「テナント誘致がうまくいかない」「2024年問題への対応策が見つからない」。そうした悩みを抱えている物流関係者は多いでしょう。物流施設は単なる保管場所ではなく、ビジネスの競争力を左右する重要な経営資源となっています。
EC市場の急拡大により需要が高まる一方で、働き方改革による制約も加わり、物流施設を取り巻く環境は大きく変化しています。
本記事では、物流施設の基本知識から最新トレンド、そして高稼働率を実現するリーシング戦略まで、物流不動産の活用に必要な情報を網羅的に解説します。
物流施設とは?
物流施設への理解を深めるためには、まず基本的な概念を正しく把握することが重要です。ここでは、物流施設の定義から従来の倉庫との違い、そして現代社会における役割について詳しく解説していきます。
物流施設の定義と役割
物流施設は、商品の保管だけでなく、仕分け、梱包、流通加工、配送など、物流に関わる様々な機能を統合的に提供。従来の単純な保管機能に加え、在庫管理システムや自動化設備を備え、効率的な物流オペレーションを実現する拠点として機能しています。
近年では、サプライチェーン全体の最適化を図る重要な戦略拠点として位置づけられており、企業の競争力を左右する存在となっています。特にEC事業者にとっては、顧客への迅速な配送を実現するための要となる施設であり、立地選定から設備投資まで慎重な検討が求められます。
倉庫と物流施設の違い
従来の倉庫が主に「保管」機能に特化していたのに対し、現代の物流施設は「物流センター」として複合的な機能を持つ点が特徴です。具体的には、設備面では床荷重1.5トン/㎡以上、有効天井高5.5m以上といった高規格な仕様が増加(※1)。また、トラックが上層階まで直接アクセスできるランプウェイや、最新の荷役機器に対応した設計が採用されています。
機能面では、クロスドッキングによる在庫を持たない通過型の運用や、流通加工による付加価値サービスの提供が可能に。さらに、WMS(倉庫管理システム)やマテハン機器の導入により、作業の効率化と精度向上を実現しています。
物流施設が果たす6つの機能と社会的役割
物流施設は現代社会において、6つの重要な機能を担っているといえるでしょう。第一に「保管機能」として、需給調整のバッファとなり、安定供給を支えています。第二に「荷役機能」により、入出庫作業の効率化を実現。第三に「流通加工機能」として、検品、仕分け、ラベリング、セット組みなどの付加価値サービスを提供しています。
第四に「包装機能」により、商品の保護と物流効率の向上を両立させ、第五に「情報機能」として、在庫情報や配送状況のリアルタイム管理を可能に。そして、第六に「輸送機能」によって、最適な配送ルートの設計と実行を担っています。
これらの機能を通じて、物流施設は社会インフラとしての役割を果たし、日々の生活や経済活動を支える重要な存在となっているのです。
物流施設の種類と特徴
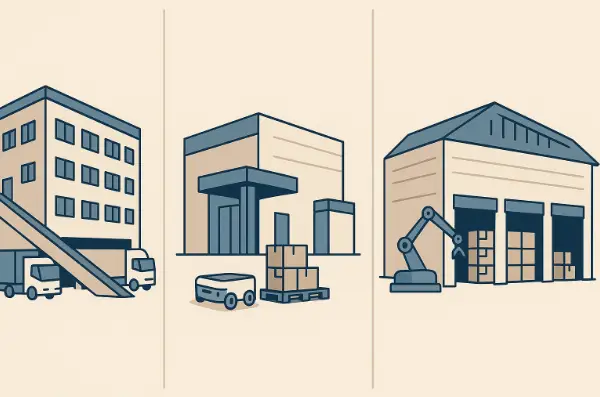
物流施設を効果的に活用するためには、ビジネスニーズに合った施設形態を選択することが重要です。ここでは、代表的な施設形態とその特徴について解説します。
マルチテナント型物流施設
マルチテナント型物流施設は、1棟の建物を複数のテナントで共同利用する形態で、近年急速に普及しています(※2)。そのメリットは、初期投資を抑えながら高機能な施設を利用できる点でしょう。
必要な面積だけを借りられる柔軟性、共用部分の管理コスト分散、立地の良い物件へのアクセスのしやすさが挙げられます。また、事業規模の変化に応じて借り増しや借り減らしが比較的容易であることも魅力です。
一方、デメリットとしては、レイアウトの自由度が制限されること、他テナントとの調整が必要になること、セキュリティ面での配慮が必要になることなどがあります。特に24時間稼働を前提とする事業者の場合、騒音や振動への配慮が求められることもあります。
BTS型物流施設(ビルド・トゥ・スーツ)
BTS型物流施設は、特定のテナントの要望に基づいてオーダーメイドで建設される施設形態です。テナントのビジネスモデルや物流特性に最適化された設計が可能で、長期的な競争優位性の確立に寄与します。
この形態が選ばれる典型的なケースとして、特殊な温度管理が必要な食品・医薬品物流、大型商品を扱うEC事業者、独自の物流システムを構築している大手小売業などがあります。初期段階から物流コンサルタントが関与し、荷物の特性や作業内容に合わせた最適なレイアウト設計を行うことで、高い作業効率を実現できます。
物流センターの種類(TC・DC・PC)と使い分けのポイント
物流センターは機能別に、TC(トランスファーセンター)、DC(ディストリビューションセンター)、PC(プロセスセンター)の3つに分類されます。
TCは通過型センターとも呼ばれ、在庫を持たずに仕分けと積み替えを主な機能とします。クロスドッキング方式により、入荷した商品を即座に出荷することで、リードタイムの短縮と在庫コストの削減を実現します。
DCは在庫型センターとして、一定期間の在庫保管と配送機能を併せ持ちます。PCは流通加工機能を重視したセンターで、値札付けや詰め合わせ、ギフト包装などの付加価値サービスを提供します。
物流施設を取り巻く最新トレンド
物流不動産業界は急速な変化の渦中にあり、新たなトレンドが次々と生まれています。ここでは、2025年の市場動向を左右する主要なトレンドについて解説します。
EC市場拡大による物流施設需要の急増
EC市場の急成長は物流施設需要を大きく押し上げる要因となっています。2020年のコロナ禍を契機に、EC化率は急上昇し、今後も継続的な成長が見込まれています。この需要増加に対応するため、大都市圏では大規模マルチテナント型施設の開発が相次いでいます(※)。
特に首都圏では、年間100万㎡を超える新規供給が続いており、施設間の競争も激化。一方で、ラストワンマイル配送に対応した都市型小規模施設のニーズも高まっており、多様化する需要への対応が求められています。
物流DX・自動化技術の導入状況と今後の展望
物流DXは単なる機械化・デジタル化を超えて、ビジネスモデルそのものの変革を目指す取り組みとして注目されています。WMS(倉庫管理システム)の導入は既に一般化していますが、最新のシステムではAIによる最適化機能が搭載され、作業動線の効率化や人員配置の最適化を実現しています。
また、AGV(無人搬送車)やピッキングロボットの導入により、省人化と24時間稼働が可能になっています。今後は、ドローンによる棚卸しや、自動運転技術を活用した構内搬送など、さらなる革新が期待できるでしょう。
脱炭素・グリーン物流への取り組み
2050年カーボンニュートラル実現に向けて、物流施設においても脱炭素への取り組みが加速。太陽光発電設備の設置、LED照明への切り替え、断熱性能の向上などが標準装備となりつつあります。
先進的な事例では、物流施設として日本初のZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証を取得した施設も登場しています(※4)。また、グリーン電力提供サービスにより、入居企業のCO2排出量を実質ゼロにする取り組みも始まっています。
2024年問題が物流施設に与える影響と対策

2024年4月から適用された働き方改革関連法は、物流業界に大きな変革をもたらしました。ここでは、物流施設の観点から見た影響と対策について詳しく解説します。
働き方改革による物流施設への新たなニーズ
トラックドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで(※5)、物流施設には新たな機能が求められています。荷待ち時間の削減が急務となっており、トラック予約システムの導入が加速。実際の導入事例では、平均待機時間を従来の7割削減した施設もあり、ドライバーの拘束時間短縮に大きく貢献しています。
さらに、勤務間インターバル制度への対応として、ドライバー向けの休憩施設の充実も重要に。シャワー室、仮眠室、食堂などの福利厚生施設を整備することで、ドライバーの労働環境改善に貢献できます。
ドライバー不足に対応する施設側の工夫
深刻化するドライバー不足に対して、物流施設側でも様々な工夫が行われてきました。女性ドライバーの増加に対応した更衣室やパウダールームの設置、高齢ドライバーに配慮したバリアフリー設計などが標準化しつつあります。
作業効率化の観点では、パレット自動供給システムや、トラックへの自動積込装置などにより、作業時間の短縮と身体的負担の軽減を実現しています。
中継拠点としての地方物流施設の重要性
長距離輸送への制約が強まる中、中継拠点としての地方物流施設の重要性が高まっています。中核都市では、中継拠点として、新たな物流施設の開発が加速(※6)。これらの施設では、ドライバーの休憩・仮眠機能を充実させるとともに、貨物の積み替え作業を効率化する設備投資が行われています。
地方自治体も企業誘致の観点から、物流施設開発に対する支援策を充実させており、用地確保や人材確保の面でもメリットがあると考えられるでしょう。
物流施設の高稼働率を実現するリーシング戦略

物流施設の収益性を最大化するためには、高稼働率の維持が不可欠です。ここでは、効果的なリーシング戦略について解説します。
テナント誘致を成功させるためのポイント
テナント誘致には、戦略的なアプローチが必要です。第一に、ターゲットとなるテナントの明確化が重要となります。第二は、競合施設との差別化で、第三は、物流会社との連携強化により、実際の物流ニーズを的確に把握することです。そのほかに柔軟な契約条件や既存テナントとの関係維持も重要になるでしょう。
内覧会の企画・運営で差別化を図る方法
物流施設の内覧会は、単なる施設見学を超えて、ビジネスマッチングの場として活用することが大切です。物流・テクノロジー・スタートアップなど、業界の最新動向を紹介するセミナーを併設することで、集客力を高められます。
実際の成功事例では、物流ロボットのデモンストレーションや、省エネ技術の実証実験などを組み合わせることで、来場者の関心を引き、施設の先進性をアピールしています(※8)。
物流会社視点でのプランニング支援の重要性
物流施設の価値を最大化するためには、実際の物流オペレーションを熟知した専門家による支援が不可欠です。物流会社の視点から見たプランニング支援により、貨物の特性に応じた最適なレイアウト設計、効率的な動線計画などが可能になります。
物流業務効率化コンサルティングの効果
専門的なコンサルティングサービスにより、作業動線の最適化、在庫配置の改善、ピッキング方法の見直しなどを実現できます。実際の導入事例では、ABC分析に基づく商品配置の最適化により、ピッキング作業時間を30%削減した例もあります(※9)。
デジタル化支援で実現する生産性向上
物流DXの推進は多くの企業にとって課題となっていますが、施設側がデジタル化支援を提供することで、このハードルを下げることができます。WMS導入支援、在庫管理システムの最適化などが挙げられます。
長期契約につながるサポート体制の構築
テナント企業との長期的な関係構築には、継続的なサポート体制が不可欠です。定期的な業務改善提案、最新技術情報の提供などが重要となります。
ESG経営に対応した施設運営のポイント
環境面では、再生可能エネルギーの活用や省エネ設備の導入、社会面では、地域雇用への貢献や働きやすい環境の整備などが重要です。
付加価値を生み出し、物流不動産ビジネスの成功を
現在の物流施設の活用において最も重要なのは、単なる不動産ビジネスとしてではなく、物流機能の提供を通じた価値創造と捉えることでしょう。立地や設備といったハード面だけでなく、運営ノウハウやサポート体制といったソフト面の充実が差別化のポイントとなります。
また、物流不動産ビジネスの成功には、専門的な知識とノウハウが不可欠です。三菱商事ロジスティクスが提供する「物流不動産サービス」は、物流会社ならではの視点で、施設の魅力を最大限に引き出す総合的な支援を行っています。
物流不動産ビジネスは今後も成長が期待される分野ですが、競争も激化しています。信頼できるパートナーとの協業により、持続可能な競争優位性を構築することをおすすめします。
<参考記事>
※1 設備紹介
※2 【2023年】物流施設の開発が止まらない6つの理由!不動産投資する価値はある?
※3 大型物流施設 2023-2025年の新規供給の見通し|東京圏
※4 「三井不動産ロジスティクスパーク(MFLP)海老名南」竣工
※6 野村不動産/物流施設に2025年度から3年で約3400億円投資、15棟開発へ
※7 Japan Office MarketView Q1 2024
※8 【8/29・30「プロロジスパーク古河4」内覧会】1時間で最大1400個!仕分けロボット実機デモ見学のラストチャンス!
Contact us.
お気軽にご相談ください
CONTACT
お問い合わせ


